過去問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に期待する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付き建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
2.宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものでないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
3.宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
4.宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。
宅建業者は取引を行うにあたり、重要事項説明書を交付して説明しなければならないが、売買に関して宅建業者が売主の場合であり、買主の場合は必要ない。
事実と異なる記載は違反。
売主は重要事項説明の相手方ではない。
重要事項説明書に記名するが、作成する必要はない。
過去問
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲土地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲土地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
2.宅地の売買における当該宅地の引き渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
3.宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
4.重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
宅建業者が当事者の場合は、相手方が取得する物件についてのみ説明。
物件の引き渡し時期は、37条書面の必要的記載事項。
支払金又は預かり金を受領しようとする場合、保全措置を講ずるかどうか、その概要は、重要事項説明書に記載しなければならない。ただし、売主である宅建業者が登記以後に受領するものについては不要。
電磁的方法による提供における承諾は、書面への出力が可能な方法又は書面です。(承諾したことを記録する)
過去問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 区分所有者の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
イ 徳地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買だ金の額並びにその支払いの時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金意外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
区分所有建物の敷地利用権の種類及び内容は説明必要。
流通業務区域内の制限の概要は説明必要。
「代金以外」の授受は説明必要。
未完成物件の重要事項説明は必要に応じ図面を交付して説明必要。
過去問
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は、宅地建物取引業者ではないものとする。
1.宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付し説明しなければならない。
2.宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
3.宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
管理組合の議決権に関する事項は説明不要。
共用部に関する計画がある場合は、その内容を説明する必要がある。
貸借で建ぺい率や容積率の説明は不要。
借賃以外の費用の説明は必要だが、保管方法の説明は必要ない。
過去問
煒建物取引業者間の取引おける宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において、重要事項説明書の交付には、相手方の承諾を得て電磁的方法により提供する場合を含むものとする。
1.建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
2.建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
3.建物の売買においては、その対象となる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
4.宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部といて30万円の預かり金の授受がある場合、その預かり金を授受しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
耐震診断の実施は、宅建業者の義務ではない。
説明の相手方が宅建業者の場合は、書面の交付のみでいい。
契約不適合責任を履行するための保証保険契約等の有無、概要は重要事項として記載必要。
50万円未満の預かり金等の保全措置は重要事項として記載不要。
過去問
宅地建物取引業者が建物の賃借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断わりない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、賃借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付し、又は相手方の承諾があれば、当該事項を電磁的方法により記録した者を提供しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
2.当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第四号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれをじっしている場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3.台所、浴室、番所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
4.宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行う時は、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
説明の相手方が宅建業者の場合は、書面の交付のみでよい。
建物状況調査の実施の有無・結果の概要は重要事項である。
建物の賃借⇒台所、浴室、便所等の整備の状況を説明する必要あり。
IT重説においても、宅建士証の提示は省略不可。
過去問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、謝っているのはどれか。なお、特に断わりのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたmのであるときは、その内容を説明しなければならない。
2.賃借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において生産することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
3.自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付し、又は相手方の承諾があれば、電磁的方法により提供して説明をしなければならない。
4.区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
昭和56年6月1日より前に着工した建物は耐震診断の説明必要。
敷金等の精算に関する事項の説明は必要。
信託の受益権の売主となる場合、宅建士の説明必要。
マンションの売買⇒修繕積立金規約、積立額は説明事項。
過去問
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する需うっ用事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五女うっ第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
2.当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
3.当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
4.当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
賃借の場合、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は不要。
賃借の場合、建設住宅性能評価書の保存状況の説明は不要。
宅建業者に石綿使用の有無を自ら調査する義務はない。
専用部分の用途その他の利用の制限について説明する必要あり。
過去問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は建物取引業者ではないものとする。
1.既存住宅の賃借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況に説明しなければならない。
2.住宅の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
3.宅地の賃借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約狩猟時における当該宅地の上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
4.建物の売買又は賃借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域作りに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、賃借の場合は説明しなくてよい。
既存住宅の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況は賃借では説明不要。
登記された抵当権は重要事項。
借地上の建物の取り壊しに関する事項は重要事項。
津波災害警戒区域に所在する事は重要事項。
過去問
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第一号の規定により市町村(特別区を含む)の長が提供する図面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者でないものとする。
1.宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷分の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
2.宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
3.宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
4.宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
水害ハザードマップが存在しない旨の説明が必要。
「洪水」「雨水出水」「高潮」のそれぞれについて提示する必要。
ハザードマップの提示と説明は貸借の場合も必要。
ハザードマップを提示し、物権概ねの位置を示して説明必要。
過去問
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く)に対して、次のアからエの発言を続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送したしました。このおでんは煮て重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧頂きながらお聞き願います。
イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
ウ この物権の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越し頂きましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明いたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事呼応の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取られたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認を頂き、私の名前を読み上げて頂けますでしょうか。そうです。読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやり取りできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
映像を視認できないIT重説は違反。
重要事項説明書は、「取引」に関わる宅建業者が作成。
重要事項説明書に宅建士の記名、宅建士証の提示が必要。
IT重説は、映像・音声、送付書類、宅建士証の確認が必要。

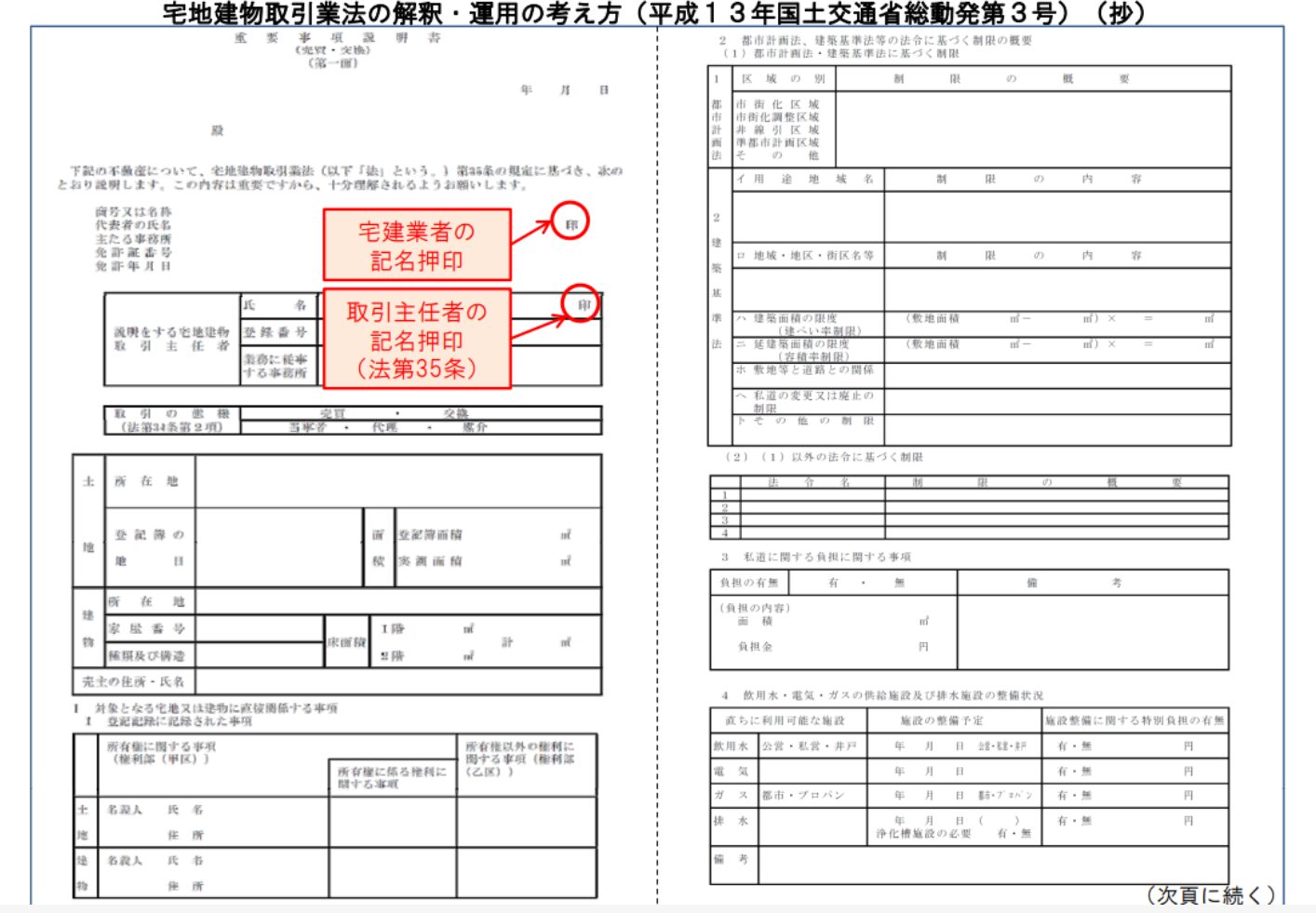



コメント