朱子学の格物解釈との相違
「格物致知」という言葉は、儒学の経典『大学』に由来する重要な概念です。朱子学では、この「格物」を「事物の理を究める」と解釈し、外部の物事を徹底的に研究することで、その理(原理・法則)を理解すべきだと説きました。
朱熹(朱子)は「格物」について、「事物に即して、その理を極めて窮める」と定義しています。つまり、森羅万象のあらゆる事物を観察・研究し、その理を一つ一つ理解していくことで、やがて天下の理を全て把握できるようになるという考え方です。
私が新聞記者として様々な取材をしていた時代を思い出します。多くの事実を収集し、分析することで真実に近づこうとする姿勢は、ある意味で朱子学的な「格物」の実践だったかもしれません。しかし、データや事実をいくら集めても、それを解釈する「心」の働きがなければ意味をなさないことも痛感しました。
王陽明の格物新説
これに対して王陽明は、「格物」を全く異なる形で解釈しました。彼は「格」の字を「正す」という意味で捉え、「格物」を「心の中の不正な思いを正す」と解釈したのです。
王陽明は若い頃、朱子学に従い、竹に向かって座り込み「竹の理」を究めようとしました。しかし、何日経っても竹の理は見出せず、むしろ病気になってしまいます。この体験から彼は、外部の事物を研究しても真の理解は得られないと悟ったのです。
彼が龍場(現在の貴州省)に左遷された時、極限の状況でついに「心外無理、心外無物」(心の外に理はなく、心の外に物もない)という境地に達しました。これが「龍場の大悟」です。
この悟りに基づき、王陽明は「格物」を「正物」と解釈し直しました。つまり、外部の事物を研究するのではなく、自分の心の中の不正な思いや欲望を正し、良知の働きを妨げるものを取り除くことこそが「格物」の本質だと主張したのです。
私は経営の現場でも、単に市場データや数字だけを分析していても、真の解決策は見つからないことが多いと実感してきました。むしろ、自分の中の先入観や思い込みを取り除き、素直な目で状況を見つめ直すことで、突破口が開けることが少なくありませんでした。
「格」の意味するところ
「格」という字には、「至る」「近づく」「正す」といった意味があります。朱子学では「至る」「極める」という意味で解釈し、陽明学では「正す」という意味で解釈したのです。
王陽明の新解釈によれば、「格物」とは外部の物事の理を極めることではなく、自分の心の中の「物」(欲望や偏見など良知を曇らせるもの)を「正す」ことを意味します。彼は「物」を「事」と同義に捉え、「事物」とは主体としての「心」が関わる様々な「事象」のことだと考えました。
この視点に立てば、研究の対象は外部の世界ではなく、自分自身の心の在り方ということになります。つまり、自己修養や内省が学問の中心となるのです。
現代の自己探求への適用
王陽明の「格物」解釈は、現代の自己探求や自己啓発の文脈でも有効です。今日、情報があふれる時代において、外部の知識を無制限に取り入れるよりも、自分の内面と向き合い、思考や感情のパターンを観察し、自己理解を深めることの重要性が再認識されています。
マインドフルネスや瞑想など、自分の心の状態に意識を向ける実践が注目されているのも、ある意味で王陽明の「格物」の現代的実践と言えるでしょう。
私自身、難病を患った後、瞑想を日課に取り入れています。外部の情報を遮断し、自分の内なる声に耳を傾ける時間は、王陽明の言う「良知」とつながる貴重な機会となっています。毎朝5時の起床後の瞑想時間は、日々の判断の軸を整える大切な実践です。
「格物」の新解釈は、現代の自己探求のアプローチにも大きな示唆を与えてくれます。外部の知識や情報を追い求めるだけでなく、自分の内なる声や直感に耳を傾け、心の中の雑念や偏見を取り除くことで、本来の自分らしさを取り戻す——これは現代人にとっても極めて有効な智慧と言えるでしょう。
次回は、陽明学と禅宗の関係について探っていきます。東洋思想の二大潮流の共通点と相違点から、より深い理解を目指しましょう。


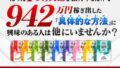


コメント